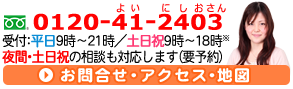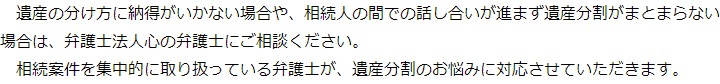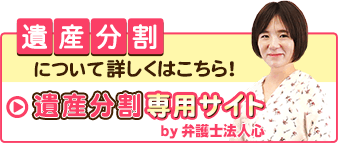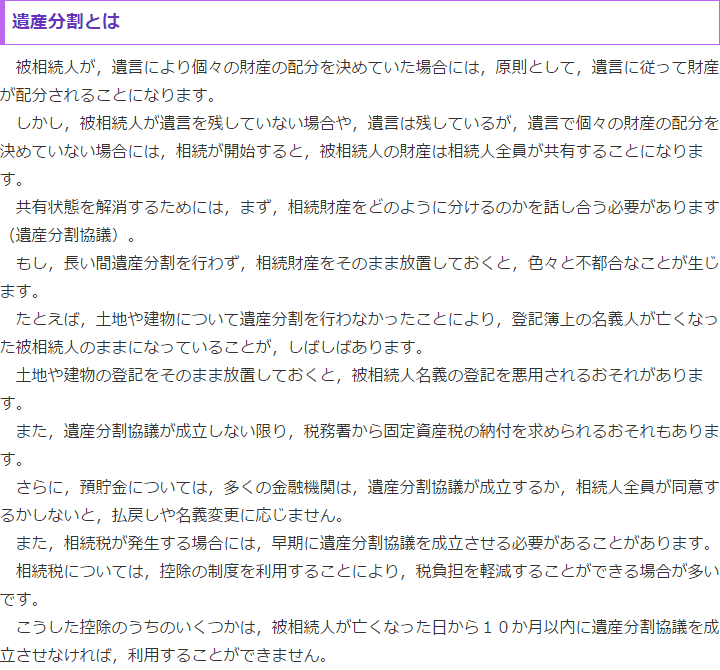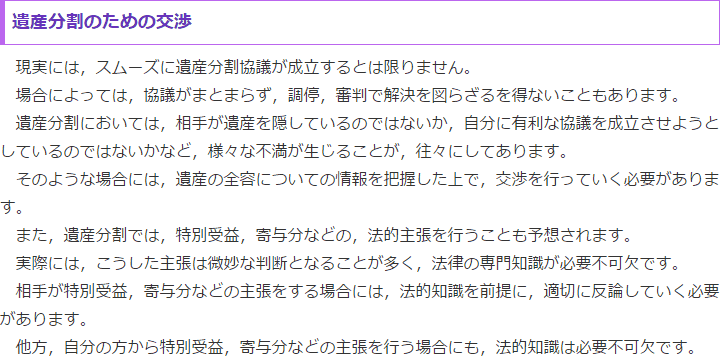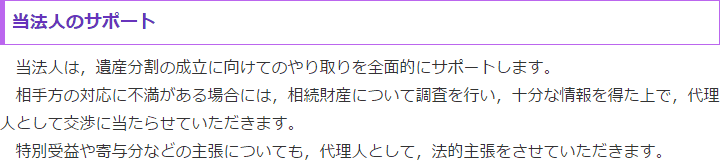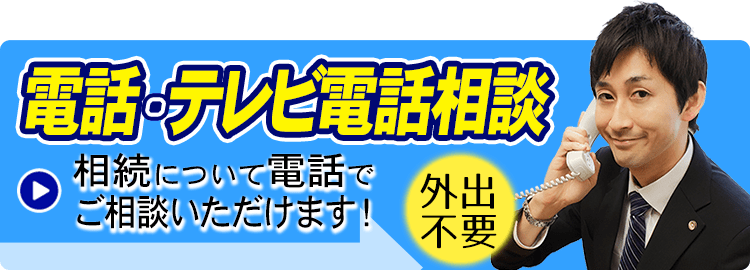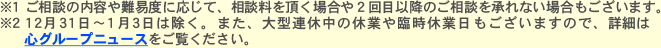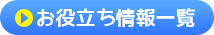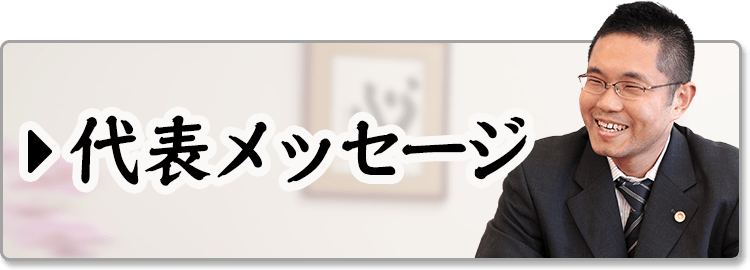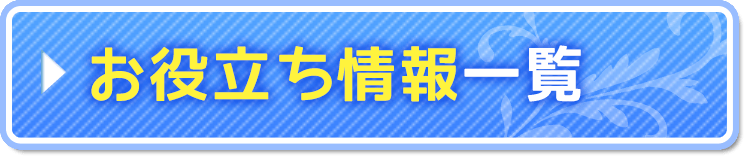遺産分割協議
遺産分割に納得がいかない場合の対応方法
1 遺産分割に納得がいかないケース
相続人間で話し合いを行うときに、遺産分割に納得がいかないと不満が出ることがあります。
よくみられるケースは、次のような場合です。
2 遺産分割の内容が不公平であるとき

遺産分割において、たとえば「相続人のうちAがすべて財産を取得することにして、Bはなしとしてほしい」といった不公平な提案を受けることがあります。
この点、Bさんが納得しているのであれば別ですが、納得できないのなら応じなくてよいのです。
その場合には、法定相続分どおりに決めることになります。
3 遺言書があるにもかかわらず、これによらずに遺産分割を行うことを提案されたとき
たとえば遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺言に基づかずに遺産分割協議を行うことができます。
その場合、遺言書どおりがよいと考えるのであれば、遺産分割協議に応じる必要はありません。
遺言書どおりにして、あとは遺留分侵害の問題とすることになります。
4 生前贈与があったとき
相続人の一部が既に生前贈与(学費や住宅取得金、結婚・子育て費用など)を受けていたような場合、その分を相続人間で考慮しないと、遺産分割が不公平となることがあります。
その場合は、生前贈与分を加算して調整することになります。
5 寄与分
相続人の一部が、被相続人の生前に、介護や事業の手伝いなどを行って、被相続人の財産の増加や維持に一定の貢献をしたにもかかわらず、他の相続人と同等に扱うと、不公平となることがあります。
その場合は、貢献した分に応じて取得分を加算することになります(寄与分といいます)。
6 遺産の範囲に争いがある場合
遺産分割協議において、たとえば遺産として現金が1000万円あったはずであるなどと一部の者が主張し、他の者がそのような現金はないといって争うようなことがあります。
遺産の範囲について争いがある場合には、遺産分割調停では扱えないので、訴訟により解決することとなります。
7 遺産の評価に争いがある場合
遺産分割において、不動産や有価証券など、評価方法によって評価に差が出るような場合があります。
この場合は、双方が、評価について意見を出し合って合意をするか、裁判所において鑑定を行って評価を決めるなどの対応をします。
遺産分割で気を付けるべき事項
1 相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。
相続人の一部が反対していたり、相続人の一部が欠けており、全員の合意が取れていなかったりするなど、相続人全員の合意が確認できない遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。
2 相続人の判断能力が十分でない場合
相続人の一人が未成年である場合、未成年であっても相続人であることは変わりがありませんので、当該未成年者も遺産分割協議の当事者の一人となります。
ただし、未成年者はまだ十分な判断能力を備えてはいませんので、未成年者が遺産分割協議に参加するにあたっては代理人を選任する必要があります。
通常、未成年者の代理人は親権者が選任されます。
ただし、当該親権者も相続人の一人である場合には、未成年者と親権者との間で利益が相反することになりますので、その場合には家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を選任することになります。
また、相続人が認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な場合には、成年後見人を選任する必要があります。
親族が成年後見人を務めていて、その成年後見人も相続人の一人であるような場合には、未成年者の場合と同様に成年被後見人と成年後見人の利益が相反することになりますので、特別代理人を選任する必要があります。
3 遺産分割協議書の記載で気を付けること
遺産分割協議書に預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。
また、不動産を記載する場合も登記簿に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。
遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。
さらに実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。
遺産分割協議書内容に即して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関に預金の解約等の手続が必要となりますが、遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続を受け付けて貰えないので、この点は注意が必要です。