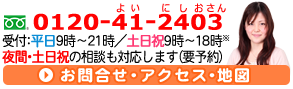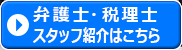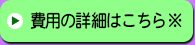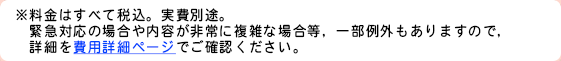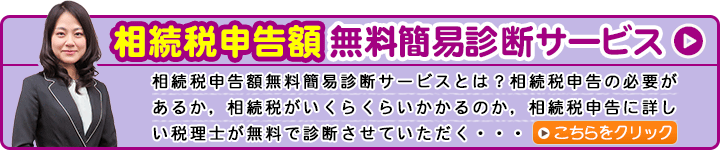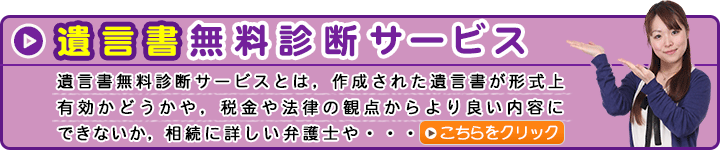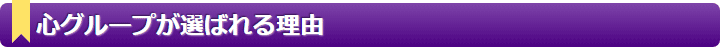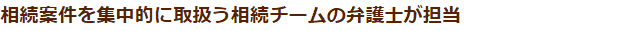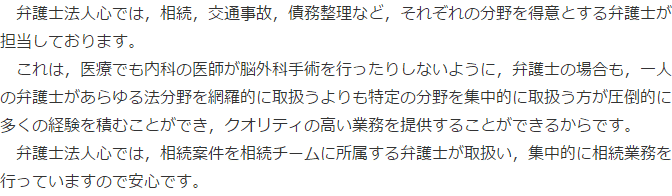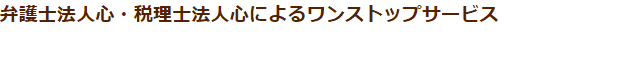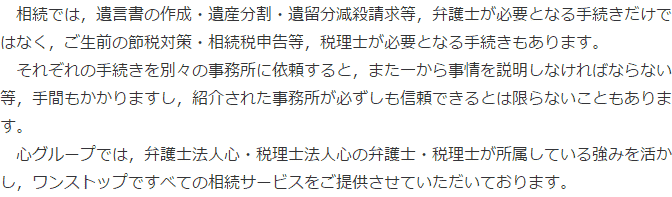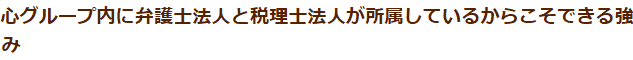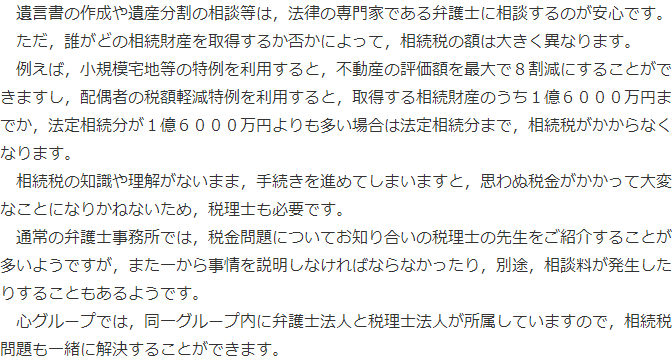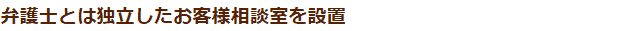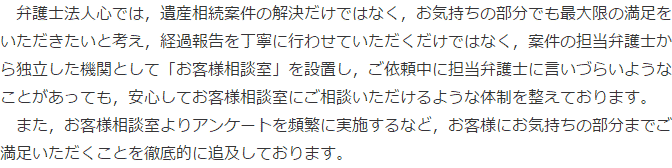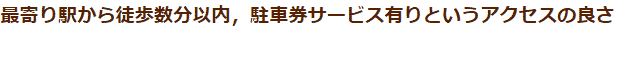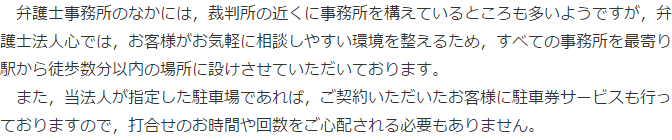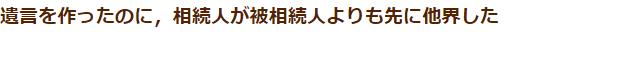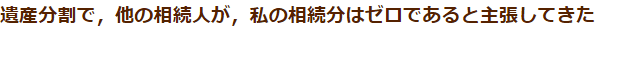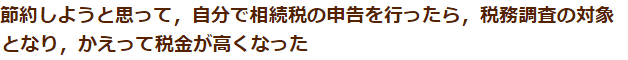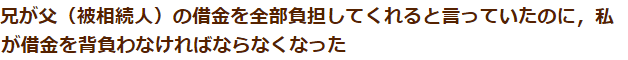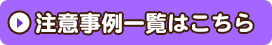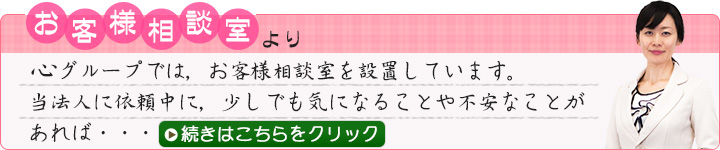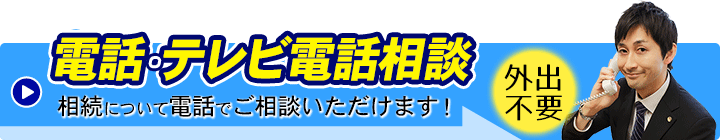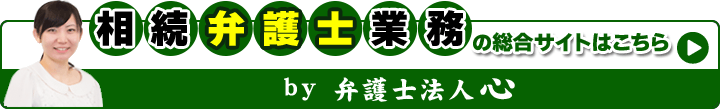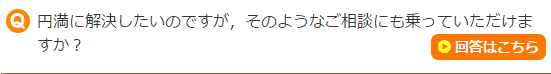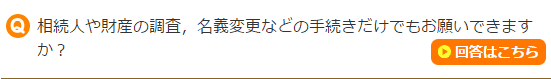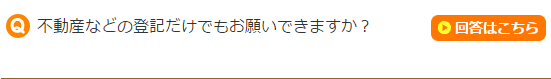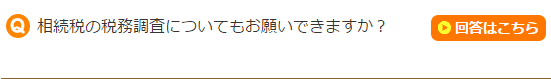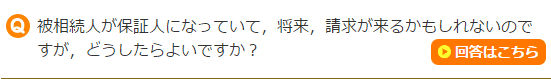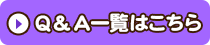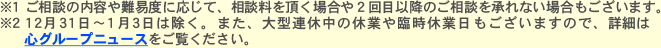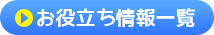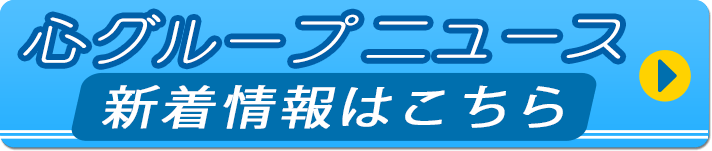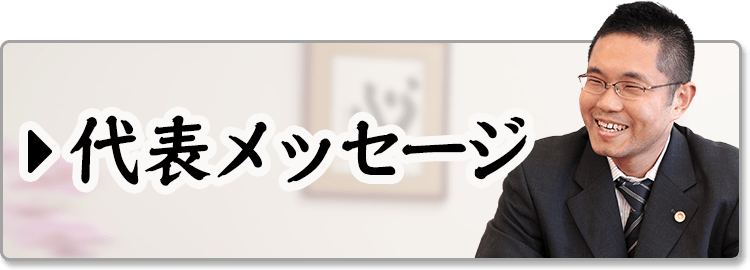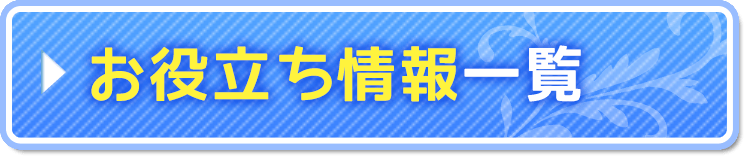業務内容
池袋で相続のご相談をお考えの方へ
相続の問題を適切に解決するため、私たちは様々な専門家と連携できる体制を整えております。その他の特徴も「選ばれる理由」にまとめておりますのでご覧ください。
専門家への相談
相続の手続きには様々な注意点があり、適切に行うためには専門家への相談をおすすめします。注意事例をまとめておりますので、池袋で相続にお悩みの方は参考までにご覧ください。
サイト内更新情報(Pick up)
2026年2月18日
遺言
公正証書遺言の費用に関するQ&A
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。これに対し、自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。公正証書遺言は、公証人がチェックして作成し・・・
続きはこちら
2026年1月9日
手続き
相続手続きの期限
相続が発生すると、葬儀を行い、悲しみに暮れる間もなく、被相続人の相続財産を把握したり、相続税を支払う必要があるかどうかを調査したりするなど、様々なことをしなければ・・・
続きはこちら
2025年12月5日
遺産分割
遺産分割の流れ
遺産分割は、亡くなった方が残した財産を、相続人の間で分けるための手続きで、相続人全員で行わなければいけません。相続人が1人でも欠けると、遺産分割は無効になってしまいます。・・・
続きはこちら
2025年11月5日
遺留分
遺留分がある場合のQ&A
法定相続人に認められた、最低限の遺産取得分のことを遺留分といいます。遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。具体的には、被相続人の配偶者、子及び・・・
続きはこちら
2025年10月10日
相続放棄
相続放棄の流れ
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産ばかりなので財産を引き継ぎたくないという場合は、相続放棄を検討することになります。・・・
続きはこちら
2025年9月4日
手続き
預貯金を相続した際の名義変更
人が死亡すると、預貯金は金融機関によって凍結され、入金も出金もできなくなります。凍結を解除するためには、銀行で相続手続きをして、預貯金を解約するか、名義を相続人に変更・・・
続きはこちら
更新された記事をご覧ください
このホームページでは、相続に関する様々な情報を掲載し、随時更新しています。更新された記事を紹介していますので、ご覧ください。
駅から近い事務所です
どの事務所も駅から数分の立地となっています。池袋駅の近くにも事務所があり、相続相談をお考えの方にもご利用いただきやすいかと思います。
相続の相談をする流れ
1 相談をするタイミングについて

相続の相談をするタイミングとしては、相続が発生する前と後に大別されます。
相続が発生する前に、相続開始後までイメージしながら、遺言書の作成や生前贈与を検討しておけば、ご本人や家族の方のライフプランとしても安心です。
その意味では、相談しようと思ったタイミングで、早めに相談するのがよいと思います。
相続が発生した後は、相続人として承継するかしないかも含め、期間内にさまざまな手続きをとっていかなければならないため、やはり早めに相談することをおすすめします。
2 相続について相談する専門家を選ぶ
相続について相談できる専門家は、主に弁護士、司法書士、行政書士、税理士です。
相続人調査や財産調査など重なる業務もありますが、特徴や取り扱う業務範囲が異なるため、ご事情に応じて相談することになります。
弁護士は、相続全般について相談できます。
当事者の代理人として交渉することができ、調停・訴訟の手続きも任せることができます。
司法書士は、不動産登記のほか、争いのない相続手続きについて相談できます。
税理士は、相続税申告や所得税の準確定申告などについて相談できます。
行政書士は、書面作成のほか、不動産登記以外の名義変更手続きについて相談できます。
事務所によっては、業務として相続をあまり取り扱っていないこともあるため、ホームページなどで事前に確認するとよいです。
事前に相談の予約が必要な事務所もありますので、相談先を決めたら、まずはお問い合わせいただくとよいかと思います。
3 相談の準備
専門家に相続の相談をする場合、当日持参するものや費用について、あらかじめ確認をしておくと安心ですし、当日スムーズに相談することができます。
相談や依頼にあたっては、本人確認のため身分証明書を提示することが一般的です。
また、相談当日に依頼する場合は、印鑑も持参するのが良いでしょう。
相談の前に、現在判明している相続人や遺産の内容、遺産の種類、遺言の有無、相続人の意向や相続に至る経緯などについて、メモを作成しておくと、効率よくスムーズに相談することができます。
4 相談・依頼について
相談の結果、内容や方針に納得して依頼することとなった場合、契約書や委任状に署名押印をし、当初支払う費用を支払うことで、依頼した業務に着手することとなります。
相続について専門家へのご相談をお考えの方へ
1 専門家に相談することの意義

相続について専門家へご相談に来られる方の多くは、相続人同士の対立に不安やストレスを感じていらしたり、先が見通せず憂鬱なお気持ちを抱いていらしたりしています。
そのような中で相談にお越しいただき、専門家と話をしているうちに、状況の整理がついたり、今後何をしなくてはならないのかの見通しがついたりするケースが多く、ご相談後に「気持ちが軽くなりました」と仰っていただけることが多々あります。
「専門家に相談する」というと、敷居が高いように思われるかもしれませんが、まずは相談することで解決の糸口を見つけられることがあります。
また、専門家に相談することで、想定していたよりも早く、かつ、スムーズに問題が解決することもあります。
自分で時間をかけて調べる手間を省くことができますし、何より、自分自身の状況に合った的確なアドバイスを受けることができます。
私たちは相続に関するご相談を原則無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
2 相談の際に持っていくとよい資料
相続の問題に対して適切な判断を下すためには、まずは相続人と相続財産を把握することが先決です。
そのため、可能であれば相続人に関する資料や財産に関する資料をお持ちいただけますと、ご相談を受けてからのアドバイスもスムーズにできます。
相続人に関する資料については、ご自身や関係する方の戸籍があると、相続人の把握がスムーズになります。
また、財産に関する資料については、財産によってご用意いただきたい資料が異なります。
例えば、不動産の場合には、不動産の特定をするために登記事項証明書があるとお話が早いかと思います。
また、不動産の評価の手掛かりになるものとして、納税通知書・課税明細書や固定資産税評価証明書等があります。
金融資産については、預金通帳の写しや、証券会社の口座明細の写しをご用意いただけますと、金融資産の把握が迅速に行えます。
また、宝石や貴金属などが遺産としてあるような場合には、宝石や貴金属の鑑定証明書があれば、財産の評価に役立ちます。
また、貴金属の場合には、貴金属に印字されている番号等によって財産の特定をすることができますので、貴金属のお写真を撮っていただくとよいでしょう。
もちろん、これらの資料が無ければ相談できないというわけではありませんので、相続にお悩みの際にはまずはお気軽に専門家にお問い合わせください。
この他に、相談したい内容を簡単にメモにしておくと、相談当日に相談したい内容を漏れなく専門家に伝えることができます。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 相続人の人数や遺産の数が不明である場合

相続問題を考えるにあたっては、まず遺産と相続人の数を把握することが必要となりますが、どちらか一方、あるいはどちらも不明な場合があります。
例えば、法定相続人が複数おり、各相続人の間で日常的に連絡を取り合っていないような場合、ご自身で相続人を把握することは難しいというケースです。
そのような場合、専門家に依頼をすることで、戸籍から相続人の範囲を調査することができます。
また、被相続人の遺産の所在が分からない場合、専門家に依頼することで財産調査をすることができます。
このように、遺産の範囲や相続人の数が不明である場合には、専門家に相談すべきといえます。
2 相続をめぐって対立が生じている場合
遺言がない場合など、遺産分割協議が必要である場合には、どのように財産を分けるかについて相続人間で対立が生じて協議が進まないケースがあります。
そのような場合、弁護士に依頼することで相手方との交渉をスムーズに進めることができたり、場合によっては、弁護士が代理人となり調停や審判等の裁判をすることができます。
特に裁判を見据える場合、紛争の処理は、数ある専門家の中でも弁護士のみが行える業務ですので、相続人間での対立が生じている場合には弁護士に相談することが相続問題の解決につながることがあります。
3 相続税が課税される可能性がある場合
遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、遺産の分割の仕方次第によって相続税額が変わる場合があります。
過大な税金を納めることになり後悔することのないように、相続税の申告が必要な場合には、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
また、遺産分割協議書や遺言の記載の仕方については、記載の仕方次第で執行ができなかったり、贈与税等の税金がかかってしまったりする場合もありますので、その記載の仕方には慎重になる必要があります。
遺言書や遺産分割協議書が無効となることを防ぐためにも、相続に詳しい専門家に相談することがよいでしょう。
相続で困った場合の相談先
1 専門家ごとに業務内容が決まっている点に注意

相続の適切な相談先というと、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの国家資格者が挙げられます。
しかし、これらの専門家であれば誰に何を依頼をしてもよいというわけではありません。
これらの国家資格を持った専門家は、それぞれの業務の範囲が法律で決められています。
例えば、相続人間の揉め事にかかわる相談や交渉は、弁護士しか行うことはできません。
また、税金に関する相談は、税理士しか受けることができません(※1)。
そのため、相談する内容に応じて相談先を決める必要があります。
※1 弁護士は、国税局長に通知をすることで、随時、税理士業務を行うことができます。
2 相続税の相談は税理士に
遺産の総額が一定以上のときは、死亡してから10か月以内に相続税の申告をしなければいけません。
相続税の申告は、複雑な財産評価や、納税額が少なくなる様々な特例を駆使して行うため、税理士に依頼をすることが安全です。
また、遺産の総額が基礎控除(※2)の範囲内であれば相続税の申告を行う必要はありませんが、そもそも遺産の総額がいくらなのか、相続税申告を行う必要があるのかが分からないという方も多いかと思いますので、まずは相談することをおすすめします。
※2 遺産から控除できる金額のことを、基礎控除といいます。遺産総額から「3000万円+600万円×(相続人の数)」の金額を控除した残りが、相続税の課税対象となります。
3 揉めていない場合は司法書士・行政書士に
財産の名義を変更したり、現金化をしたりするために、相続手続きを行う必要があります。
このような相続手続きは、
・相続人が一人しかいない場合
・遺産分割協議書が既にある場合
・遺言書が存在する場合
など、相続人間で揉めていない場合に限り、司法書士・行政書士が行うことができます。
ただし、土地の名義変更は司法書士しかできないため、遺産に不動産がある場合は司法書士に相談をした方がスムーズかと思います。
4 どこに相談していいか分からない場合は弁護士に
相続人間での揉め事や、相続放棄などの裁判所での手続き、遺言作成などの法律相談は弁護士にしかできないため、弁護士に相談してください。
もっとも、弁護士は、不動産の名義変更や銀行の預金解約など、大抵の手続きを広く行うことができます。
そのため、誰に何を相談すればいいか分からない場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
5 相続でお困りの場合は、お気軽にご連絡ください
私たちは、弁護士・税理士などが連携して相続のご相談に対応できる体制を整えております。
ご相談内容によっては、弁護士兼税理士など、複数の資格を持つ専門家が対応させていただく場合もあります。
相続のお悩みが生じるごとに、相談先を探すとなると時間がかかってしまいますので、相続をスムーズに進めるためにも、相続のお悩みは相続をトータルサポートできる私たちにご相談ください。
相続を依頼する場合の専門家の選び方
1 弁護士に依頼するべき場合

相続人同士で対立が生じている場合など紛争が生じている場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、紛争処理ができる唯一の専門家ですので、対立が生じている場合または対立が見込まれる場合には、最初から弁護士に相談するべきです。
弁護士に依頼するメリットとしては、裁判手続も含む紛争処理を見越したアドバイスを受けられるという点です。
また、紛争に伴う精神的負担や相続に伴う手続上の負担を弁護士に対応してもらえるというのも、弁護士に依頼するメリットといえます。
2 税理士に依頼するべき場合
相続財産が多く、相続税の申告が必要な場合には税理士に依頼することをおすすめします。
相続税額は、相続財産の評価や遺産の分配の仕方、特例の適用の有無によって大幅に変わります。
また、将来、次の相続が見込まれる場合には、数次相続を見越した節税対策が必要になってきます。
そのため、相続税申告の経験・実績が豊富な税理士に相談することが大切です。
3 司法書士に依頼するべき場合
遺産に不動産が含まれ、不動産の登記名義の書き換えが必要となる場合には、司法書士に依頼することもできます。
特に、相続した不動産を売却して相続人全員で分ける場合や、不動産についていた抵当権や質権等の担保権を抹消したいような場合には、不動産登記の書き換えも複雑になることがあります。
こういった場合には、登記手続の専門家である司法書士に依頼することを検討するとよいかと思います。
4 その他専門家を選ぶ場合のポイント
相続手続には、不動産知識や、保険や預貯金に関する金融知識など幅広い知識が求められます。
これらの知識を有している方が、より適切な対応が期待できます。
そのため、専門家に依頼する場合には、その専門家の専門分野だけでなく、不動産や金融などの隣接分野についても精通している専門家に依頼することが大切です。
各専門家が協力できることの強み
1 相続のお悩みをまとめて解決

相続の手続きには様々な種類のものがあり、その手続ごとに必要となる専門家が異なります。
しかし、そもそも、「どの専門家に何を相談すればいいのか」というのは、なかなか難しい問題です。
また、遺産分割協議や裁判所での手続きは弁護士へ、相続税など税金の話は税理士へ、不動産の名義変更であれば司法書士へといった形で、それぞれ別の専門家を探して、それぞれに状況を説明して依頼をするというのは大変です。
この点、様々な分野の専門家同士が協力できる体制が整っていれば、相続のお悩みを役割分担しながら解決することができます。
相談する側からすれば、一つの窓口に相談して、あとはまとめて任せることができます。
2 解決が早くなる
相続の手続きには、大量の戸籍をはじめ、様々な資料が必要になり、必要書類を集めるのに時間がかかることもあります。
相続の手続きごとに別々のところに依頼をした場合、それぞれの専門家が同じ資料を集めた結果、二度手間になってしまうこともあり、時間が余計にかかってしまうケースも考えられます。
しかし、専門家同士で協力することができれば、資料を共有して無駄を省き、効率よく手続きを進め、スムーズに解決まで進むことができます。
3 貰える遺産の金額が変わってくることも
遺産分割と切っても切り離せないのが、税金の話です。
遺産を相続したら相続税が、相続した不動産や株式を売却したら譲渡所得税がかかります。
たとえば、評価額が額面上同じであっても、特例の適用の有無や、路線価による評価減等により、受け取る財産により課税される相続税の金額が違ってくることはよくあります。
遺産分割協議書上は同じ金額でも、相続税が安くなるように分割ができれば、最終的に手許に残る金額が多くなります。
そのため、税金面も考慮した遺産分割を行うことが大切であるといえます。
税理士と弁護士が協力することができれば、遺産を分ける段階で、将来発生する税金のことまで見越して協議ができるというメリットがあります。
また、一人の相続人が他の相続人の権利も含めて不動産を丸々引取り、不動産の仮の評価金額を決めて他の相続人に権利分の金額を支払うという分割方法があります(代償分割)。
しかし、引き取った不動産が予定より高く売れるかどうかはわかりません。
不動産会社と連携し、事前にいくらくらいで売れるかをあらかじめ確認できれば、不動産が高く売れず損をしてしまうリスクを減らせます。
このように、専門家同士で連携ができれば、事前に打ち合わせることで、より良い相続のプランを立てていくことができるといえます。
弁護士に相続の相談をするべきタイミングとは
1 どのタイミングで弁護士に相談すればいい?
相続の問題についてお悩みを抱えている方の中でも「どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのか分からない」と迷われる方も多いかと思います。
今回は、相続について弁護士に相談するべきタイミングについて説明します。
2 遺言を作成するとき

ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることがないように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いかと思います。
法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。
どちらの場合も、民法で形式要件が定められており、形式要件に違反した遺言は無効となります。
作成した遺言が無効となってしまうことを防ぐために、遺言を作成するタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士は、内容面についてもより良いものとなるようにアドバイスすることができ、例えば、相続発生後に起こることが予想されるトラブルも見越して、遺言の作成のお手伝いをさせていただくことができます。
3 相続が発生したとき
相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。
しかし、それぞれ調査するためには、相応の費用と労力がかかります。
また、慣れていない方からすると、どこで何を調べるべきなのか見当が付かないこともあるかと思います。
さらに、仮に調査ができたとしても、相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々から相続人の間でトラブルが生じることが予想されます。
弁護士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、ご自身でそれらの調査をする必要はありません。
また、現存する資料から分かる範囲で漏れなく相続人および相続財産の調査をすることができます。
4 遺言が発見されたとき
遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか、判断することは難しいかと思います。
また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所の手続きを経なければなりませんが、そのような手続きの仕方についても不安を覚える方は多いかと思います。
弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続きについても、適切なアドバイスを受けることができます。
5 遺産分割協議を行うとき
遺産分割をしようと思っても、他の相続人と意見が対立してしまい、遺産分割協議がまとまらないケースもあります。
このような時には、弁護士が代理人として入ることで、他の相続人との遺産分割交渉がスムーズに進む場合があります。
また、どうしても任意での交渉がまとまらない場合には、調停や審判といった裁判手続きを行うことがあり得ます。
この時にも、弁護士に依頼することで、裁判手続の見通しについて適切なアドバイスを受けることができます。
意見の対立が生じていなかった場合であっても、遺産分割について弁護士に相談することで、適切な遺産分割についてアドバイスを受けることができ、よりよい相続となる可能性が高いです。
そのため、遺産分割の際は、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
6 弁護士への相談はお早めに
相続については、早めに弁護士に相談することによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続きを進められる場合があります。
相続について、少しでもお悩みが生じた場合には、一度弁護士にご相談することをおすすめします。
相続のご相談から解決にかかる時間
1 スムーズであれば3か月程度

相続のご相談においては、まず、遺言書の有無、相続人の範囲や相続財産の内容などを確認し、その具体的な事情によって、手続きを選択していく必要があります。
したがって、個別の事情によって、解決に至る時間は異なります。
たとえば、相続人が一人で、相続財産が預貯金のみ、口座も一つだけといった場合であれば、早ければ2週間程度で終わるかもしれません。
しかし、通常は、遺言書の有無、相続人・相続財産調査を行って、相続人間で遺産分割協議を終えるのに、スムーズに進んだとしても、3か月程度はかかるでしょう。
相続放棄を行う場合には、自己のために相続開始があったことを知ってから3か月以内に行わなくてはならないので、その意味でも、まずは3か月を念頭におきながら、迅速に調査を進めていく必要があります。
2 調査内容や協議の進行により、6~9か月程度
相続人が不明である場合や相続人同士が日頃から交流がない場合は、連絡を取るまでに時間を要してしまいます。
相続財産の種類が多い場合などは、調査や財産評価が大変です。
このようなことから、上記のようなケースでは、解決までにもう少し時間がかかることがあります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっているため、これに間に合うように遺産分割協議を進めます。
3 進行次第では、数年かかることもある
相続財産の種類が多い場合や、分けにくい遺産が相続財産の大半を占めているような場合、相続人同士でもめているような場合などは、遺産分割協議に時間がかかり、場合によっては数年かかるようなこともあります。
遺産分割協議が難しい場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立て、月に1回くらいのペースで話し合いを行い、それでもまとまらなければ審判により解決することとなります。
そのほか、相続人や遺産の範囲などに争いがある場合には、訴訟を行うこともあります。
このように、相続について相談をしてから解決までにかかる時間については、ケースバイケースで、個別の事情により大きく変わってきます。
どのようなケースでも、できるだけスムーズに進められるように、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。
相続に強い専門家に依頼するメリット
1 相続案件には広い知識と経験が必要

相続案件では、相続に関する法律を熟知している必要がありますし、相続税など、税に関する知識も欠かせません。
不動産が関わっている場合には、不動産の名義変更手続きだけでなく、不動産の評価の方法、売却の方法などについての知識も必要になってきます。
さらに、相続の分野では法律の改正や税制の改正が頻繁にされますし、重要な問題について判断がされた裁判例や、最新のトレンドも把握しておく必要があります。
これらの知識に加えて、相続ではどのようなことが紛争になりえるのかについての経験も必要です。
なぜなら、紛争になる原因が分かっていなければ、それについての対策を検討することができないからです。
このように、相続案件を適切に進めていくためには、広い知識と経験が必要です。
そのため、相続に関する豊富な経験・知識を持つ相続に強い専門家に依頼することにメリットがあるといえるのです。
2 すべての専門家が相続に強いわけではない
すべての専門家が相続に強いわけではありません。
弁護士や税理士といった専門家は、相続の他にも幅広い業務分野があります。
そのため、すべての専門家が日頃から相続案件を多く扱っているわけではありませんので、相続案件を中心的に扱っていなければ、相続に関する知識や経験が蓄積されていきません。
さらに、特定の専門家に依頼しても、その専門家が扱える範囲が限られてしまうことがあります。
すなわち、遺言書の作成や遺産分割協議などは、法律の専門家である弁護士に依頼することになりますが、相続税対策や相続税申告については、税金の専門家である税理士に依頼することになります。
このように、それぞれの業務を別々の専門家に依頼する必要があるのが通常ですが、相続に強い専門家に依頼をすれば、複数の分野の知識が必要となることを把握しているため、日頃から連携を取り合っており、両方の業務分野に対応できることもあります。
そのため、相続案件を依頼する場合には、相続に強く、さらに、複数の分野の専門家と連携できる体制を整えている専門家を選ぶことにメリットがあるといえるのです。
不動産評価に強い専門家に相続を相談すべき理由
1 不動産評価で相続する金額が大きく変わる

相続とは切っても切り離せないのが、不動産評価です。
現金や預貯金は、その金額がそのまま相続財産となるため分かりやすいですが、不動産は、その資産価値をいくらと考えるのかによって変わってきます。
遺産分割、遺留分請求、生前対策など、不動産評価が必要な場面は多くあります。
不動産評価は、不動産会社によりバラつきがあり、増減する要素や相場により、金額が数百万〜数千万変わることも珍しくありません。
相手の出してきた不動産査定を鵜呑みにしたら、相場とかけ離れており、数百万円損をしたなどということもあります。
2 市役所の「評価額」ではダメな理由
不動産の評価方法の一つに、市役所が送ってくる納税通知に書かれている「評価額」というものがあります。
しかし、遺産分割の際には「時価」という、実際に不動産を売買したときの金額を基準として話し合いが行われます。
固定資産評価額は、時価の70%程度の金額と言われているため(※)、これを知らずに遺産を分けてしまうと、大損をしてしまうこともあります。
※70%はあくまで目安で、時価が固定資産税の5倍以上になるケースもあれば、逆に固定資産評価の方が高くなるケースもあります。
例)
預金:5000万円
不動産:時価5000万円、固定資産評価額:3500万円
を、AとBの2人で、2分の1ずつ分ける場合
①固定資産評価額(3500万)を基準にした場合
A:不動産(3500万円)+預金750万円
B:預金4250万円
②時価(5000万)を基準にした場合
A:不動産(5000万円)
B:預金5000万円
となり、固定資産評価額を基準に話し合いをしてしまうと、Bは本来なら貰えた預金750万円の分だけ損をしてしまいます。
3 支払う税金も変わってくる
相続税の申告で用いる不動産の評価額は「路線価」というもので、固定資産評価額とは別の基準となります。
相続税評価額の計算は、土地の形が長方形から何%歪んでいるかなど、複雑な計算のうえで行われます。
この計算が適切に行えていないと、税金を払いすぎてしまったということにもなりかねません。
また、土地については、税金が少なくなる様々な特例がありますが、これらの特例の使い方次第で、納める税金の額は大きく変わってきます。
そのため、相続税について相談する際も、不動産評価に強い専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄をしたい場合の相談先
1 相続放棄の期間と手続きについて

⑴ 相続放棄の期間
相続放棄は、相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産や借金などの債務を、一切受け継がないとするものです。
相続放棄は、相続開始後、いつでもできるわけではなく、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなくてはなりません。
⑵ 期間を経過してしまった場合
相続放棄は、原則として3か月以内に行わなければならないものの、3か月を過ぎた場合であっても、特別な事情があれば、例外的に相続放棄が認められることもあります。
そのため、3か月が過ぎてしまったからといってあきらめてしまわず、事情によっては、期間経過後であっても専門家に相談されることをおすすめします。
⑶ 相続放棄の手続き
相続放棄は、他の相続人に対し放棄することを伝えれば成立するというものではなく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所において申述をしなければなりません。
そのほか、限られた時間内で、財産の調査や戸籍謄本等の取得などを行う必要があります。
このように、期間や手続きなどが定められていることから、すみやかに専門家に相談し、必要な書類を集め、方針を確認して、準備を進めていかなければなりません。
2 相続放棄の相談先
相続放棄について相談できる専門家としては、弁護士と司法書士が考えられます。
弁護士は、相続放棄申述書の作成はもちろん、裁判所に代理提出を含めた手続きを行うことが可能です。
また、遺産分割協議の調整、調停、審判、遺留分侵害額請求など、相続きの手続き全般について行うことができます。
そのため、全体像を見据えて、必要な相談や依頼をすることができます。
これに対し、司法書士は、相続放棄についていえば、相続放棄申述書の作成や必要書類の取得等を依頼することができます。
しかし、司法書士は、相続放棄申述書の代理提出ができないなどの制約があるほか、紛争性のある業務(遺産分割協議の調整や調停、審判、遺留分侵害額請求など)に対応することはできません。
なお、行政書士は、相続放棄申述書の作成を行うことができませんので、そもそも相談先とはなりません。
相続財産の調査も専門家にお任せください
1 相続財産の調査はどうして必要なのか

相続が発生したとき、まずは、相続財産が何であるかを調査する必要があります。
遺産が明らかになっていないと、誰がどの遺産を相続するのか、相続をしないという選択をすべきか、判断できません。
特に、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄をすることで、一切承継しないで済むことになりますので、財産の内容を把握することは大切です。
また、遺産分割協議を行うにしても、後から新たな相続財産が判明するとトラブルの原因となりかねませんので、相続財産を確定する必要があります。
そのほか、一定額を超える相続財産がある場合には、相続税申告を適切に行う必要がありますが、そのためにも相続財産を把握する必要があります。
2 相続財産の調査はいつまでに行うか
相続放棄の期限は、相続があることを知ってから3か月以内であるため、万一マイナスの財産が多い場合には相続放棄の手続きをとれるように、相続財産の調査を進めるのが一般的です。
すでにおおよその相続財産の内容を知っていて、プラスの財産が多いため、相続放棄を考えなくてよいという場合でも、相続税申告の期限もあるため、やはり相続開始から3か月程度を目安として、早めに進めていくことが多いと思います。
3 相続財産の調査はどのように行うか
相続財産の調査は、亡くなった方の相続財産に関する手がかりをもとに、一つ一つ各機関に問い合わせていくことになります。
相続人がご自身で行うことも可能ですが、必要書類を揃えるのはなかなか地道で煩雑な作業であるため、慣れていないと難しいかもしれません。
また、各機関が平日の営業時間にしか電話や窓口対応をしていないことも多いため、色々な手続きの期限に間に合うように、作業時間を確保できるかという問題もあります。
そのため、相続財産の調査も専門家に依頼したいというご要望も少なくありません。
場合によっては、役割分担をしながら進めることもあるかもしれません。
相続財産について、どのような方針で調査するか、どのような財産をどのような範囲で調査をするのか、費用がどうなるのかも含めて、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。
遺産分割をする際に調査・検討すること
1 遺産の調査

遺産分割を行うにあたり、遺産を明確にする必要があります。
調査しなくても大丈夫だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、遺産の全体像をきちんと把握しておくことは遺産分割において重要です。
なぜなら、万が一、遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合は、その遺産の分割方法について再度相続人全員で協議しなければいけなくなり、手間がかかりますし、新たに見つかった遺産の価値などによっては、トラブルの火種になるおそれがあるからです。
そのため、遺産分割前の遺産の調査は、適切に行うことが大切です。
しかし、中には、被相続人との連絡が途絶えており、相続人がどのような財産を有していたのか分からないというケースがあります。
このような場合、まずは財産の調査から始めることになります。
具体的には、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。
不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。
また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。
2 法定相続人の調査
遺産分割を進めていくうえでは、そもそも誰が相続人となるのかを把握する必要があります。
また、遺産分割協議を行うには、相続人全員で協議をする必要がありますので、法定相続人を調査・把握することは必要不可欠の作業となります。
具体的には、被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。
3 寄与分・特別受益の検討
遺産分割で争いになりやすい点として、「寄与分」「特別受益」が挙げられます。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人の相続分を増やす制度です。
「被相続人の介護をしていた」「被相続人に資金の援助をしていた」といった場合には、寄与分として認められる可能性があります。
特別受益とは、共同相続人の特定の者が被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与や遺贈を受けた場合の利益をいいます。
特別受益と認められた場合には、特別受益を受けた相続人の相続分は特別受益分を控除して定められます。
「家を建てる際に被相続人から資金の援助を受けた」等の事情がある場合、特別受益として認められる可能性があります。
寄与分や特別受益に該当するかどうかについては、過去の裁判例をベースに事案ごとに判断を要するため、専門的な知見が必要です。
寄与分や特別受益に当たると思われる事情がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
代襲相続と数次相続
1 既に相続人が亡くなっている場合の相続

既に相続人が亡くなっている場合にはその子が相続人になるという代襲相続のルールについてはご存じの方が多いのではないでしょうか。
しかし、代襲相続と数次相続との区別は難しく、混同してしまっている方もいらっしゃいます。
ここでは、代襲相続と数次相続の違いについてご説明します。
2 代襲相続と数次相続の違い
⑴ 代襲相続
代襲相続は、相続発生時点で相続人が既に亡くなっている場合に、その子(その子も亡くなっている場合には孫等)が代わりに相続人となるというルールのことです。
例えば、令和5年に亡くなったAに、長男Bと長女Cがいたところ、Bは平成20年に既に亡くなっており、Bには妻Dと子E、Fがいたというケースでは、Aの相続について、代襲相続人であるE、Fが相続人になります。
このケースでは、Bが既に亡くなっていることを示す除籍謄本等のほか、Bの出生から死亡までの全ての戸籍を取り付け、E、F以外の子がいないことを確定させる必要があります。
注意していただきたいのは、この場合には、Bの妻Dは相続人ではないということです。
⑵ 数次相続
数次相続とは、前の相続の分割等が終わっていない間に、次の相続が発生してしまうことです。
先ほどのケースで、令和5年にAが亡くなった後、分割協議をしないうちに、続けて長男Bが亡くなってしまったというケースです。
この場合には、代襲相続ではなく、相続が連続している数次相続ですので、Aの遺産につき2分の1の権利を有しているBが亡くなり、Bの相続人であるD、E、Fのそれぞれが、4分の1、8分の1、8分の1ずつ、Aの相続権を相続していることになります。
⑶ 亡くなった順番によって相続人の範囲が変わることがある
このように、亡くなった順番により、相続人の範囲が異なることになりますので、注意が必要です。
3 数次相続は複雑になりがち
土地の登記名義を祖父、曾祖父の代から変えていないといったように、相続を放置していると、多くの場合、数次相続が発生してしまっています。
特に兄弟相続が絡んでくると、相続人が数十人に上ってしまい、相続分も何十分の1、何百分の1、何千分の1になってしまうこともあり、手に負えなくなります。
数次相続が発生すると、相続人や相続財産の調査が複雑になり、慎重な対応が求められる場面もあります。
相続人の範囲や法定相続分がややこしくなると、ミスが生じる可能性が高くなってしまいますし、関係者が増えると手続きも煩雑になります。
できる限りスムーズに相続を行うことができるように、遺産分割協議は、時期を逸しないうちに解決するべきだと言えます。
相続が発生した場合に必要な戸籍謄本等について
1 相続手続きには戸籍謄本等が必要

相続の手続きをする際、最初に立ちはだかる壁が、戸籍謄本等の取得です。
戸籍謄本は、相続の手続きをする金融機関や法務局に対して、相続関係を証明するために必要であり、必要な全ての戸籍謄本がないと、相続手続きを進めることができません。
ケースによっては、分厚い束になるほどの戸籍謄本を取得しなければならないこともあります。
そして、相続の手続きにおける戸籍の取得をさらに難しくしているのが、相続のパターンにより、必要な戸籍が変わってくるという点です。
ここでは、基本的な相続のパターンごとにご説明します。
2 子(または配偶者と子)が相続人であるケース
子は、常に相続人になりますので、子が相続人のパターンは必要な戸籍謄本類が一番少ないケースです。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本、戸籍謄本、原戸籍と、相続人の現在戸籍で足ります。
なぜ、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるのか、ご質問を受けることがあります。
その理由は、亡くなられた方が出産(認知)や養子縁組等をしたか、していないかを確認するためです。
3 親(または配偶者と親)が相続人であるケース
親が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、亡くなられた方に子がいないことを示す書類が必要になります。
亡くなられた方に以前に子がいたものの、子が死亡したという場合には、その子の出生から死亡までの戸籍謄本等についても取得する必要があります。
さらに、相続人となる親につき、両親がご存命なのか、一方のみなのかを示す書類も必要になるため、亡くなられている相続人がいる場合には、死亡を示す戸籍謄本等も必要になります。
4 兄弟が相続人であるケース
兄弟が相続人となるパターンの場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の現在戸籍のほか、まず、直系尊属が全て亡くなっていることを示す必要があります。
すなわち、亡くなられた方の直系尊属全員が死亡していることを示す戸籍謄本が必要となります。
この時、120歳くらいまでは存命である可能性があると考え、現時点で存命であれば120歳以下である方の全てにつき、死亡を証明する必要があります。
次に、兄弟の確定及び、存命か亡くなっているかの確認のため、兄弟それぞれにつき、戸籍を取得する必要があります。
5 相続手続きでお困りの方はご相談ください
上記のように、相続手続きで必要な戸籍謄本は、誰が相続人なのかによって異なります。
相続に慣れていないと、どのような戸籍謄本を取得しなければいけないのかという点から調べなければいけないため、時間がかかりますし、本当に合っているのか不安を覚える方もいらっしゃることと思います。
また、取得した戸籍謄本を読み解くことが難しいということもあるかと思います。
相続手続きに関する不安・疑問についてご相談にのらせていただきますので、お困りの方は私たちにご相談ください。